

冨永愛が京提灯工房を訪れ、伝統工芸に挑戦する特別企画
冨永愛が挑戦!京提灯作りの奥深さ
毎週水曜日の夜に放送される「冨永愛の伝統to未来」では、冨永愛が京都の伝統工芸「京提灯」の工房を訪問する様子が描かれます。4月2日の放送では、江戸時代から続く京提灯の老舗「小嶋商店」を訪れ、伝統の技を体験しました。
京提灯の歴史と特徴
「小嶋商店」は、創業が寛政年間という歴史ある工房。南座の大提灯を製作し、200年以上にわたって京都の美しい景観を照らしてきました。現在では、日本国内はもちろん、海外からの発注も相次ぎ、世界的にその名を知られています。
京提灯は主に2つの作り方があります。一つは「巻骨式」で、竹ひごを螺旋状に巻いて作る方法。もう一つは「地張り式」で、こちらは細く割いた竹を型に沿わせ、平行に組んで作ることで長持ちします。特に屋外で頻繁に使用される京提灯は、頑丈さが求められるため、地張り式が採用されることが多いのです。
難攻不落の提灯作り
工房では、九代目の小嶋護さんと彼の息子の諒さんが、今もなお地張り式の提灯を手作業で作り続けています。冨永愛は、まず「糸釣り」という作業に挑むことに。職人にとって非常に重要なこの工程は、竹の骨を糸で繋ぐ作業です。
「ずっと糸を緊張させた状態で繋いでいくのが大変です」と諒さんが説明します。実際に冨永愛が挑戦すると、最初は手ごたえを感じるものの、糸の緊張を維持するのは難しく、彼女は「やばい、やばい!これ一回緩んできちゃうと全部緩んできますね」と苦戦していました。
和紙の美しさ
次に待ち受けるのは「紙張り」。骨に和紙を貼るこの作業は、特に難しく、冨永愛は「これメチャクチャ難しいです。全然出来ない!」と嘆く場面も。職人の技を目の当たりにし、その熟練した手さばきに感心しきりでした。彼女は「凹凸のある部分に綺麗に張れるなんて、やっぱり凄いですね」と脱帽。
字入れと新たな挑戦
さらに、字入れや絵付けの作業は九代目の護さんが担当。その作業は、凹凸がある提灯の表面に絵や文字を綺麗に入れるもので、ミスが許されない難しさがあります。冨永愛もこの作業に挑戦し、「これも見た目より本当に難しくて、凸凹しているので真っすぐ塗れない!」と四苦八苦していました。
新たな商品開発へ
時代の変化に伴い、提灯の需要が減少する中でも、小嶋商店は新しい商品開発に力を入れています。小嶋護さん曰く、「もちろん伝統的な使われ方も重要ですが、新しい需要の創出が必要だと思っています」。その結果として生まれたのがミニ提灯「ちび丸」です。この製品は気軽に提灯作りを楽しむことができるキットで、願いや絵を入れてオリジナルの提灯を手作りできます。
未来を紡ぐ伝統工芸
今回の特集を通じて、冨永愛は伝統工芸の素晴らしさと、そこで働く人々の情熱を伝えています。また、「北陸の伝統を未来へ紡ぐ」というコーナーでは、昨年の能登半島地震で被害を受けた伝統工芸の方々への視聴者からのメッセージも紹介。
この特別企画は4月2日(水曜日)夜10時から、BS日テレにて放送されます。ぜひ多くの方々にご覧いただき、伝統文化の魅力を感じていただきたいと思います。




トピックス(その他)



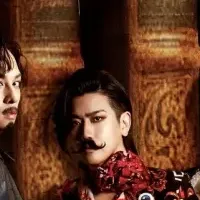
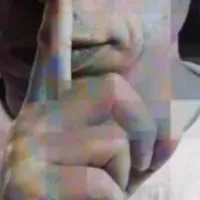

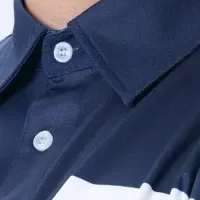



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。