

石川県とスポーツ界、復興支援に向けた新たな協定を締結
石川県とスポーツ界、復興支援に向けた新たな協定を締結
一般社団法人スポーツを止めるなが、スポーツ界の力を結集し、災害復興を支える試みを強化するため、石川県との包括連携協定を結びました。この協定は、復興支援をスポーツを通じて実現するための新しい取り組みとして注目されています。
災害支援活動の発足
今回の取り組みは、災害復興に向けた想いを抱くアスリートやスポーツ団体が、実際の被災地と連携し、持続可能な支援へとつなげていくことを目的としています。特に、令和6年に発生した能登半島の震災や豪雨災害に対し、早急な支援活動を行い、その結果を次の災害への備えにも活かすことを目指しています。
包括連携協定の内容
この協定には、主に以下のような内容が含まれています。1つ目はスポーツを介した復興支援、2つ目はスポーツの開催を通じた復興、そして3つ目は両者が協力して行うその他の支援活動です。これにより、双方のニーズとリソースをしっかりと結びつけながら、復興を進めていくことを目指しています。
石川県の知事である馳浩氏は、「スポーツを通じての活動が復興を後押ししている」とその意義を強調。復興には長い期間が必要であるため、継続的な支援の重要性が再認識されています。
スポーツ団体の具体的なアクション
スポーツを止めるなは、被災地支援活動の具体的な施策を2つの柱に分けています。一つ目は、有志アスリートによる現地でのさまざまな活動や、スポーツ大会を通じた集まり、高齢者へのフレイル対策の支援です。
二つ目は、被災地の情報を継続的に発信することで、状況を広く伝え、支援モデルをスポーツ界内で共有することです。
これに加え、アスリートと地域の子どもたちが「顔の見える関係」を築くことで、長期的な支援ができるようにする「ワンスクール・ワンアスリート」プログラムも導入されます。これにより、コミュニケーションや支援のきっかけを少しずつ作り出し、地域と深く結びつくことで、支援が地域にとって意味のあるものになるよう努力します。
具体的な支援活動の成果
先日、慶應義塾大学および早稲田大学の学生たちが協力し、輪島市でボランティア活動を行いました。普段はライバルである両校が手を組んで支援にあたることで、地域に新たな活力をもたらしました。この活動を通じて、地域の実情を学び、さらなる支援へとつなげていくことでしょう。今後も日本オリンピック委員会などと連携しながら、幅広いスポーツ団体との協力が期待されます。
まとめ
スポーツ界と地域が手を結ぶことで、災害復興に向けた取り組みが新たな形で進化し始めています。中長期支援をしっかりと実現し、必要な情報を発信しながら、被災地の声を反映することで、持続可能な支援が展開されることを期待します。

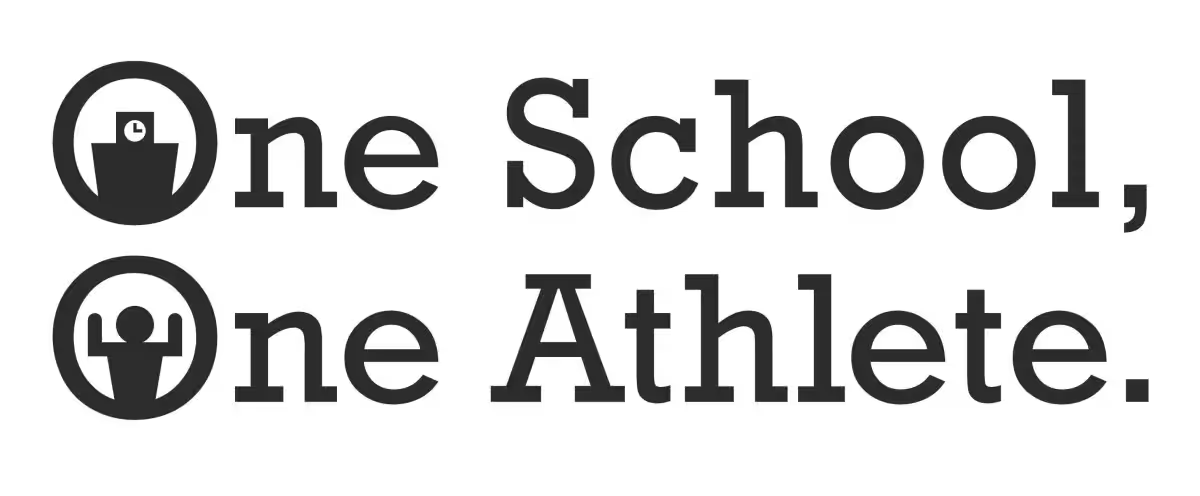


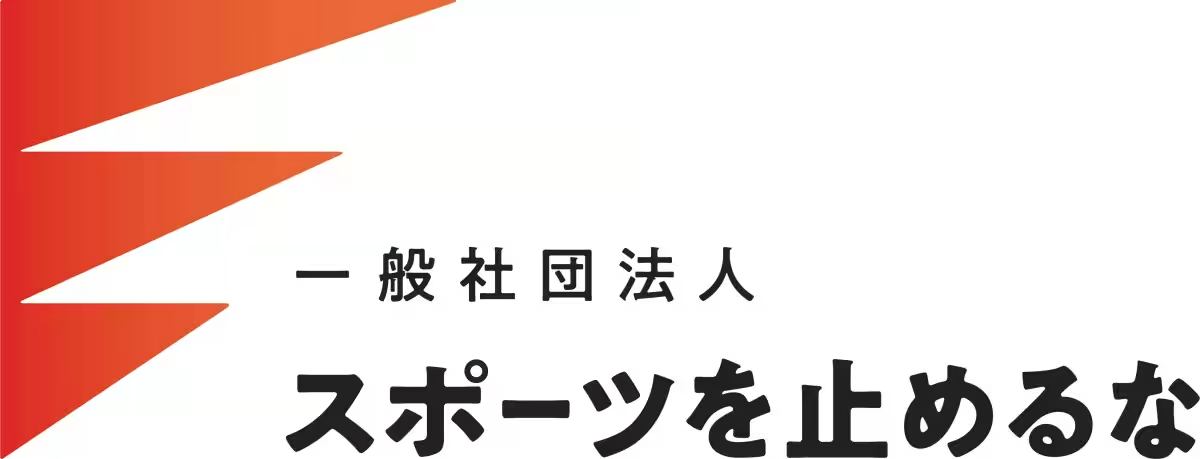



トピックス(その他)


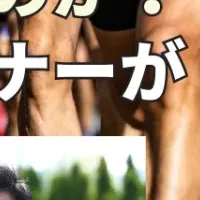

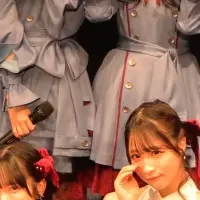
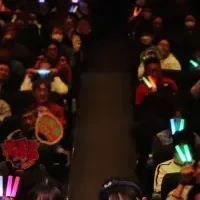




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。