
観客への台本貸出によるバリアフリーの実現を目指して
きこえない・きこえにくい観客のための台本貸出への意識調査
ポールトゥウィンホールディングスの関連企業、Palabra株式会社が発表した調査結果は、映画や舞台における「きこえない・きこえにくい方」に対する台本貸出サービスの導入状況を明らかにしました。この調査は文化庁から委託を受けた「令和6年度障害者等による文化芸術活動推進事業」の一環として行われました。
調査の背景
2022年には、舞台芸術事業者向けに鑑賞サポートに関する意識調査が実施され、その結果、来たる「合理的配慮の義務化」が約半数の事業者にとって未知の領域であったことが指摘されました。しかし、実施意欲は高く、9割以上が「条件が整えば実施したい」との回答を示しました。主な課題は資金面にあり、予算が限られているため、鑑賞サポートの導入が困難という現実が浮き彫りになったのです。
台本貸出の現状と意義
義務化を迎えた現在、資金的に導入しやすい方法として、多くの作品で「台本貸出」が開始されています。しかし、実際には観客からのさまざまな声が寄せられており、それらは今後のサポート体制において無視できない要素です。
調査の結果、台本貸出の形式や内容に関して、観客のニーズをより深く理解することが重要であると確認されました。観客の声をもとに、より効果的なサービスの提供を目指す必要があります。
実際の声
ある40代女性は、公演決定当初には情報保障の予定がなかったが、事業者に代理で問い合わせたことで、台本タブレットの貸出が可能となったと語っています。このような対応が、観客の安心感を高める一助となっています。
さらに、30代女性は、問い合わせ先がメールであれば気軽に連絡できるが、電話しかない企業の場合にはコミュニケーションの難しさを指摘。事業者からのアフターフォローに感謝したとの声もありました。
調査の概要
この調査は、2024年11月21日から12月9日まで行われ、76名からの回答を得ました。その中で、回答者の51.4%はろう者であり、25.7%は難聴者でした。回答者の聞こえの状況も多様で、多くは生まれつきの聴覚障害を持っていることがわかりました。
鑑賞サポートの意義
舞台や映画において「鑑賞サポート」は重要な役割を果たしています。このサポートは、字幕や手話通訳、音声ガイド、台本貸出など多岐にわたり、聴覚障害者や視覚障害者が文化芸術を楽しむための支えとなります。このような支援を通じて、より多くの人々が文化にアクセスできる環境が整うことでしょう。
結論
今後、台本貸出や他の鑑賞サポートがさらに拡充されることで、きこえない・きこえにくい方々の鑑賞体験が向上することが期待されます。観客の声を積極的に取り入れることで、より良いサービスの提供につながると信じています。
トピックス(その他)


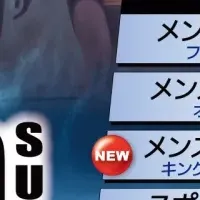
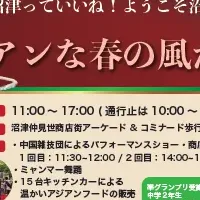




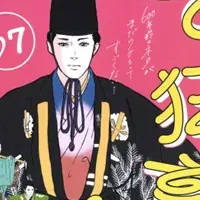

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。