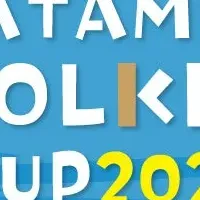
大学入学者選抜の実態と分析に関する最新調査報告
大学入学者選抜の実態と分析に関する調査
全国の大学における入学者選抜の実態を把握し、さまざまな分析を行った文部科学省の報告書が発表されました。本報告書は、大学入学者選抜における多様性や公平性、また新たな基準の必要性について深く掘り下げています。これからの教育にどのような影響があるのか、一緒に見ていきましょう。
調査の背景
大学入学者選抜制度は、教育の質を確保するために重要な役割を果たしています。しかし、時代の変化に伴い、選抜方法の多様化が求められていることも事実です。具体的には、志願者の背景や能力を正しく評価し、多様な人材を受け入れるための仕組みが求められています。文部科学省はこのような実態を把握するために調査を開始しました。
主な調査内容
この調査では、大学の入試における各種選抜方法がどれだけ利用されているのか、またその効果について分析が行われました。例えば、一般入試、推薦入試、AO入試などの比率や、それぞれの試験の特徴、志願者の傾向などが詳しく報告されています。
調査結果のハイライト
調査結果によれば、近年では推薦入試やAO入試の割合が増加していることが確認されました。特に、推薦入試を利用する志願者が増える一方で、一般入試の受験者は減少傾向にあるとのことです。これは、高校教育の中での教育改革が影響しているとも考えられます。また、評価基準の多様化が進む中で、学力だけでなく、いわゆる「人物評価」が重視されるようになっています。
教育現場への影響
この調査は、教育現場に直接的な影響を与えることが予想されます。教育機関は、この報告書を元に、選抜基準の見直しや、出願者を対象とした支援策の強化などを進める必要があります。特に、受験生が自分を確実にアピールできるような支援体制の構築が求められています。
施策の提案
今後文部科学省は、調査結果を基に追加の施策を検討する方針です。特に、入試制度の改革や、高校と大学の連携強化が重要なキーワードとなっています。これにより、大学が求める人材を適切に選出できる体制が整うことを目指しています。
まとめ
大学入学者選抜は、今後ますます変化する教育環境に対応して進化していく必要があります。この調査から得られた知見は、教育改革に向けた重要な指針となるでしょう。一般の皆さんも、この報告書を通して、大学入試の新たな流れを知ることができる貴重な機会です。今後の動向にぜひ注目していきましょう。
トピックス(その他)
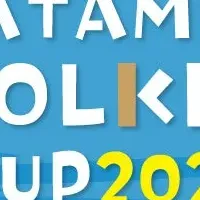

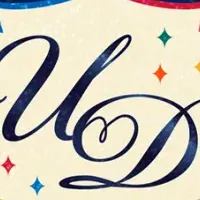

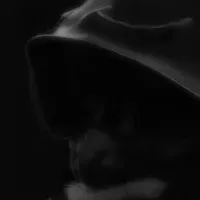
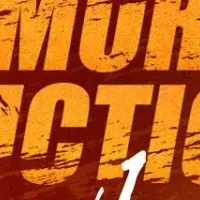
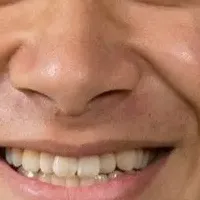



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。